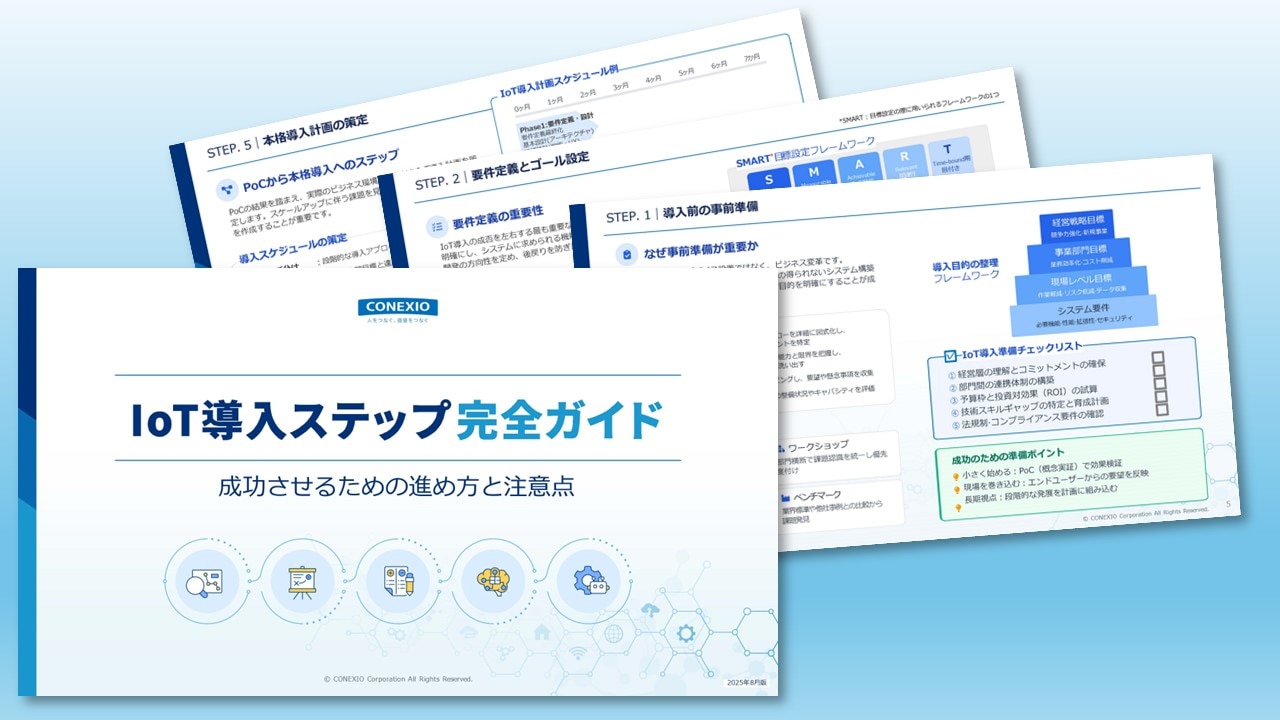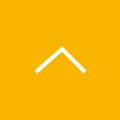設備保全 DX化の理由とIoTの効果
設備保全は、社内の生産設備やシステムを安定稼働させて、事業を継続するために欠かせない取組みの一つです。設備停止や故障などによる損害を防ぐには、定期的な点検とトラブルの早期発見が重要です。
しかし、設備保全には専門的な知識・技術が求められるほか、現場の人手不足も深刻化していることから、「点検・監視業務の負荷が大きい」「保全業務や管理体制が属人化している」といった課題を持つ企業もあります。
このような課題に対応するために、設備保全のDX(Digital Transformation:デジタル・トランスフォーメーション)化を図ろうと検討している方も多いのではないでしょうか。
この記事では、設備保全の概要をはじめ、DX化が求められる理由について解説します。
目次[非表示]
- 1.設備保全DXとは何か
- 1.1.設備保全の基本概念
- 1.2.DXの定義とその意義
- 2.設備保全DXが求められる理由
- 2.1.人手不足の影響と対策
- 2.2.技術継承の重要性
- 3.DXを支える具体的技術
- 3.1.IoTの効果と活用例
- 3.2.AIの役割と応用事例
- 3.3.クラウド技術の利用とそのメリット
- 4.設備保全DXの具体的ソリューション
- 4.1.スマートIoTプラス【プラント統合監視】
- 4.2.予知保全システム
- 4.3.保全計画の自動化と管理
- 4.4.設備保全におけるデジタルツインの活用
- 5.設備保全DXの導入ステップ
- 5.1.課題の整理とデータ確認
- 5.2.プロジェクト管理と実行
- 5.3.導入後の効果測定と改善策
- 6.まとめと今後の展望
▼おすすめの関連記事
「設備・機器に対する異常検知とは? 機械学習による対策方法」
「設備保全とは? 種類やIoT導入による効果について解説 」
「製造業が直面する課題と人材難・IT化・技術継承の解決策 」
設備保全DXとは何か
設備保全の基本概念
設備保全とは、生産設備や機械、IT機器などを安定して稼働させるために、点検、メンテナンス、修理などを行う業務のことです。
これらの設備・機械は、長く使用し続けると経年劣化によって消耗・故障したり、性能が低下したりします。このような状態で使用すると、設備停止が起こり、業務や生産ができなくなる、不良品が発生するなどのトラブルが発生する可能性があります。こうしたトラブルを防ぐためには、日常的に設備・機械の点検・検査を行い、劣化具合に応じて部品交換や修理などを行うことが欠かせません。設備保全は、大きく3つの種類に分けられます。
▼設備保全の種類
種類 |
業務内容 |
予防保全 |
保全計画に基づいて一定の間隔で点検・修理・部品交換を行う |
事後保全 |
不具合・故障・性能低下が起きてから修理や部品交換を行う |
予知保全 |
不具合・故障の兆候を検知して、修理や部品交換を行う |
DXの定義とその意義
DXとは、ICTやIoTなどのデジタル技術を活用して、ビジネスモデル、社会、人々の生活を変化させることです。
設備保全DXが求められる理由
人手不足の影響と対策
1つ目は、現場の人手不足です。
設備保全の現場において、人手による点検・巡回を行っている場合、労力・時間がかかりやすくなります。人手不足が発生していると、巡回点検の業務に十分な時間を割けない、または必要人材を投入できないといった課題につながります。限られた人材で効率的かつ適切な保全業務を行うには、IoTやITシステムを活用して、人手による巡回点検を効率化・省人化することが必要です。
▼ドローンやセンサーを活用した設備保全DXの事例はこちら
技術継承の重要性
2つ目は、設備保全業務の技術継承です。
設備保全業務では、機械に関する専門知識や、点検・修理に関する技術が必要です。人手による管理をベースとした設備保全を行っている場合、熟練者の知識や経験に依存しやすく、業務が属人化しやすいといった課題があります。過去の故障事例や修理対応などの情報が社内で蓄積されていなければ、若手人材の育成も進みません。
設備保全業務の技術継承を促進させるには、IoTやITシステムを導入して、保全活動に関わるデータを収集・蓄積・共有できる環境の構築が求められます。また、若手人材の育成に向けて、AR(Augmented Reality:拡張現実)技術を取り入れながら、遠隔での作業指示や、作業方法の標準化を図ることも重要です。
DXを支える具体的技術
IoTの効果と活用例
設備保全のDX化に欠かせない技術として、IoTが挙げられます。センサーやIPカメラを通じて、設備・機械の稼働状況をデータとして収集・可視化することで、さまざまな効果が期待できます。IoTの導入によって得られる効果には以下が挙げられます。
▼IoTの導入効果
- 業務の効率化
- 品質の向上
- 技術・ノウハウの継承
- 予知保全の実現
IoTを導入することにより、設備機器の遠隔監視や作業の遠隔指示を行えます。管理者が設備モニタリングを実施すれば、人手による定期的な巡回点検も不要です。
現場の作業員による点検・修理が必要な場合には、技術者がバックヤードにいながら、遠隔地から作業指示を行うことで、業務の効率化・時間短縮に貢献します。
また、保全計画の作成、データ登録などをシステム上で自動化することによって、人的ミスや作業漏れを防ぎ、品質の向上も期待できます。
AIの役割と応用事例
AIは設備保全において、データ解析や予測モデルの構築に重要な役割を果たします。例えば、過去の故障データを基にした機械学習アルゴリズムによって、故障の予兆を検知し、予防保全を行うことが可能です。また、異常検知の自動化により、人的リソースを削減しつつ、高精度な監視を実現します。
クラウド技術の利用とそのメリット
クラウド技術を活用することで、設備保全のデータをリアルタイムで共有し、関係者がいつでもどこでもアクセス可能になります。これにより、データ管理の効率化と災害時のデータ保護が強化されます。さらに、クラウド上でのデータ解析により、迅速な意思決定を支援します。
設備保全DXの具体的ソリューション
スマートIoTプラス【プラント統合監視】
「工場全体の状態をひと目で把握したい」「現場の省人化・自動化を進めたい」――そんなご要望に応える大規模プラント向けIoT化支援サービスです。 複数の装置・センサーを一元監視でき、現場の稼働状況や異常をリアルタイムで把握することができます。管理・保守の効率化、人手不足対策、設備の最適運用によるコスト削減など、設備保全DXを強力に支援します。
▼スマートIoTプラス【プラント統合監視】のご紹介はこちら
予知保全システム
予知保全システムは、IoTセンサーやAI技術を駆使し、設備の異常を事前に検知することが可能です。これにより、設備の計画的なメンテナンスを実施でき、無駄なコストを削減します。具体的には、振動センサーを使用して機械の異常振動を検知し、故障の兆候を早期に発見する機能があります。
▼IoTを活用した予知保全ソリューション事例はこちら
保全計画の自動化と管理
保全計画の自動化は、AIを用いたデータ解析により実現されます。これにより、設備の状態に応じた最適な保全計画を自動で生成し、作業の効率化を図ります。管理者は手動での計画作成から解放され、より戦略的な業務に集中できます。
設備保全におけるデジタルツインの活用
デジタルツインは、物理的な設備のデジタルコピーを作成し、リアルタイムでのシミュレーションを可能にします。これにより、設備の運用状況を仮想的にテストし、最適な運用方法を模索することができます。結果として、故障リスクの低減や保全コストの削減につながります。
設備保全DXの導入ステップ
課題の整理とデータ確認
設備保全DXの導入に際しては、まず現状の課題を整理し、必要なデータを確認することが重要です。これには、設備の故障履歴やメンテナンス記録を精査し、改善点を洗い出す作業が含まれます。データの正確性と一貫性が、DXの成功を左右します。
プロジェクト管理と実行
プロジェクト管理は、DX導入の成功の鍵です。計画段階から実行、評価までの各フェーズを明確にし、進捗を綿密に管理します。特に、導入初期には小規模な試験運用を行い、結果を基に調整を加えながら進めることが推奨されます。
導入後の効果測定と改善策
DX導入後は、定期的な効果測定が必要です。KPIを設定し、業務効率やコスト削減効果を数値化します。得られたデータを基に、さらなる改善策を講じ、継続的なプロセスの最適化を図ります。
まとめと今後の展望
設備保全のDX化は、企業にとって不可欠なプロセスとなっています。人手不足や技術継承の課題を乗り越えるために、IoTやAI、クラウド技術を活用したDX化は大きな効果をもたらします。今後は、さらに高度な技術が普及し、設備保全のDX化が一層進むことが期待されます。
「アナログな保全体制で負荷がかかっている」「熟練者の技術・ノウハウをうまく活用できていない」などの課題をお持ちの場合は、DX化を進めてはいかがでしょうか。
▼おすすめの関連記事
「設備・機器に対する異常検知とは? 機械学習による対策方法」
「設備保全とは? 種類やIoT導入による効果について解説 」
「製造業が直面する課題と人材難・IT化・技術継承の解決策 」